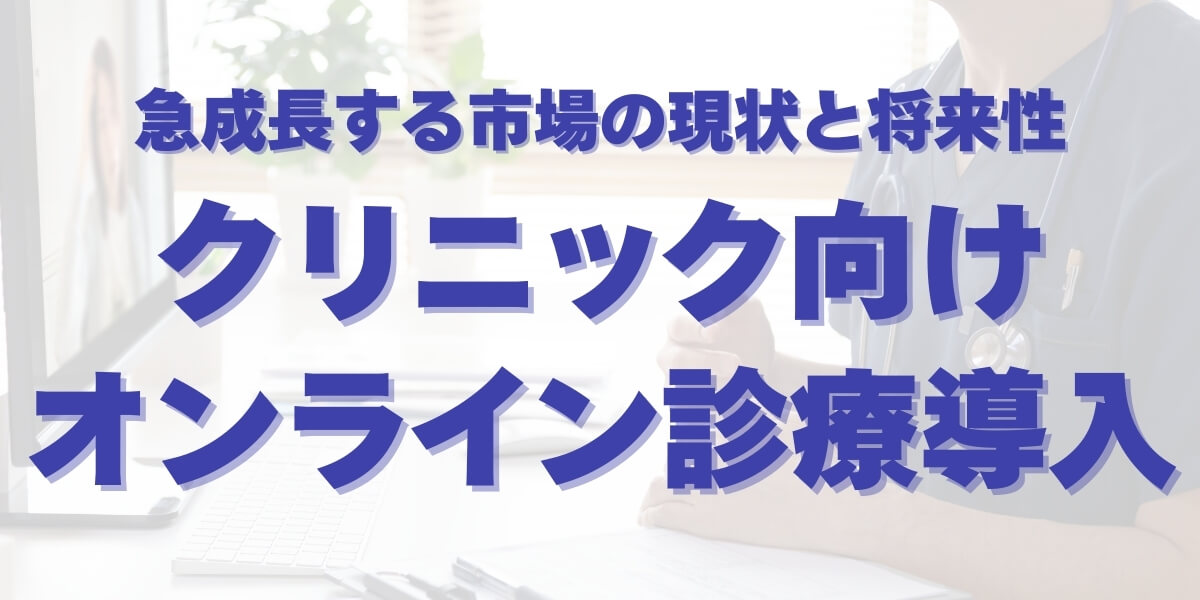「オンライン診療ってクリニックにとって本当に必要なの?」
「導入費用に見合う効果があるのか分からない」
「市場規模や将来性はどうなっているの?」
このような疑問を持つ医療機関経営者は多いのではないでしょうか。
クリニック向けオンライン診療導入は、新型コロナウイルス感染症を契機として急速に普及が進んでいる新しい医療提供体制です。
本記事では、クリニック向けオンライン診療導入市場の現状と将来性について、最新のデータと事例を基に分かりやすく解説します。
市場規模や成長予測を理解することで、今後のクリニック経営戦略を立てる際の重要な判断材料となるでしょう。
この記事で分かること
• 日本のオンライン診療市場規模と成長予測の詳細
• クリニック導入率の推移と普及を阻む要因
• 主要システム提供企業の動向と競争状況
分かりやすく解説しているので、ぜひお読みください。
目次
クリニック向けオンライン診療導入市場ってどれくらい?
オンライン診療市場は想像以上に急成長を続けており、今まさに「導入のタイミング」を迎えています。
具体的な市場規模と将来性について、分かりやすく解説しているので、ぜひ読んでみましょう。
日本のオンライン診療市場規模と成長予測
日本におけるオンライン診療市場の規模は、近年急速な拡大を続けています。
富士経済の調査によると、オンライン診療システム市場は2020年の約32億円から、2035年には106億円超まで成長すると予測されています。
引用元:富士経済「2022年 医療連携・医療プラットフォーム関連市場の現状と将来展望」
実際に、世界の遠隔医療市場規模は2022年に約12兆6,700億円と評価され、2030年までに約41兆5,000億円に成長すると予測されています。
日本市場も世界的な成長トレンドに追随し、政府の医療DX推進政策と相まって急速な市場拡大が見込まれているのが現状です。
引用元:モルドールインテリジェンス社調査
クリニック導入率の推移と普及状況
クリニックでのオンライン診療導入率は、着実に増加傾向を示しています。
総務省の調査によると、2020年4月時点で電話・オンライン診療に対応した医療機関は10,812件(全体の9.1%)でした。
しかし2021年4月には16,843件(全体の15.2%)まで増加し、わずか1年間で導入率が約6ポイント上昇しています。
引用元:総務省「令和3年版情報通信白書」
さらに注目すべきは、オンライン診療料の届け出を行っている医療機関数の変化です。
| 年度 | 届出機関数 | 対前年比 |
|---|---|---|
| 2022年7月 | 5,494件 | – |
| 2023年10月 | 10,108件 | 約84%増 |
2022年の診療報酬改定後、届け出医療機関数は倍近く増加しており、制度改善の効果が明確に現れています。
引用元:厚生労働省「オンライン診療等の診療報酬上の評価見直しについて」
世界市場との比較から見る日本の現状
日本のオンライン診療普及率は、世界の主要国と比較して低水準にとどまっています。
アメリカでは新型コロナウイルス感染拡大前の普及率が約20%だったのに対し、規制緩和後には約60%まで急増しました。
一方、日本は規制緩和後でも約15%程度にとどまり、先進国の中では普及が遅れている状況です。
この差の要因として、診療報酬の水準差や医療機関・患者双方のITリテラシーの違いが挙げられています。
世界市場では年平均成長率44.4%(2022-2028年)という驚異的な成長が予測されており、日本市場も今後大幅な成長余地があると考えられています。
引用元:march「オンライン診療のシェア率は?普及しない理由や患者満足度の実情を紹介」
これまでの対面診療との違い
オンライン診療導入により、従来の対面診療とは大きく異なる医療提供体制が構築されています。
単なる診療方法の変化ではなく、診療報酬体系や患者アクセス方法、クリニックの運営コスト構造まで根本的な変革をもたらしています。
具体的な違いについて詳しく解説しているので、ぜひ読んでみましょう。
診療報酬体系と収益構造の変化
診療報酬の体系が、対面診療とオンライン診療で大きく異なります。
対面診療との違いを明確にするため、以下の項目で比較します。
・対面診療初診料: 288点
・オンライン診療初診料: 253点
・対面診療再診料: 75点
・オンライン診療再診料: 75点
再診料については対面診療と同水準に調整されましたが、初診料では依然として35点の差が存在します。
しかし、オンライン診療では患者の交通費負担がなく、医療機関側も院内感染対策費用や待合室運営コストが削減できるため、総合的な収益性は向上する場合が多いのが特徴です。
患者アクセス方法と診療プロセスの違い
患者のアクセス方法が根本的に変化しています。
従来の対面診療では、患者は必ず医療機関に足を運ぶ必要がありました。
一方、オンライン診療では以下のような新しい診療プロセスが確立されています。
- オンライン予約: 24時間いつでも予約可能
- 事前問診: 来院前にデジタル問診票を完了
- ビデオ通話診療: 自宅等から診察を受診
- オンライン決済: アプリ内で会計処理完了
- 処方薬配送: 薬局からの直接配送サービス
このプロセス変化により、患者の通院時間が平均2-3時間短縮され、特に働き世代や育児中の女性から高い評価を得ています。
実際に、オンライン診療を受診した患者の約85%が満足と回答しており、利便性向上の効果が明確に現れています。
引用元:総務省調査結果
設備投資と運営コストの比較
初期投資と運営コスト構造も大きく変化しています。
オンライン診療導入には専用システムの導入費用がかかりますが、長期的には運営コストの削減効果が期待できます。
| コスト項目 | 対面診療 | オンライン診療 |
|---|---|---|
| 初期投資 | 待合室・診察室設備 | システム導入費用 |
| 月額固定費 | 施設維持費 | システム利用料 |
| 変動費 | 院内感染対策費 | 通信費・サポート費 |
特に注目すべきは、オンライン診療により院内混雑が緩和され、感染対策や清掃コストが大幅に削減される点です。
新型コロナウイルス対策として実施していた追加の清掃・消毒作業が不要となり、年間運営コストを10-15%削減したクリニックも報告されています。
クリニック向けオンライン診療導入が注目される理由
オンライン診療導入への注目度が急激に高まっている背景には、複数の構造的要因があります。
新型コロナウイルス感染症への対応として始まった規制緩和が恒久化され、患者ニーズの変化と政府政策が相まって市場拡大を後押ししています。
具体的な注目理由について詳しく解説しているので、ぜひ読んでみましょう。
新型コロナ後の制度整備と規制緩和効果
制度面での大幅な規制緩和が市場拡大の最大の要因となっています。
2020年4月の時限的措置として始まった初診からのオンライン診療は、その後段階的に恒久化されました。
2022年4月の診療報酬改定では、オンライン診療の施設基準が見直され、より多くの医療機関が参入可能となりました。
・事前の対面診療期間: 6ヶ月から3ヶ月に短縮
・対象疾患: 大幅に拡大し、ほぼ全疾患が対象
・診療報酬: 対面診療との格差を段階的に縮小
さらに、厚生労働省は「オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針」を策定し、2030年までの普及目標を明確に設定しています。
引用元:厚生労働省「オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針」
患者ニーズの変化と利便性向上
患者側のニーズ変化が市場拡大を強力に後押ししています。
新型コロナウイルス感染症の経験により、患者の医療機関に対する期待が大きく変化しました。
従来重視されていた「対面での丁寧な診察」に加えて、「感染リスクの回避」と「利便性の向上」が重要な選択基準となっています。
実際の調査結果では、以下のような患者ニーズの変化が確認されています。
・感染リスク回避: 患者の74%が院内感染を懸念
・時間効率性: 働き世代の68%が待ち時間短縮を重視
・継続性: 転居後も同じ医師の診療を希望する患者が増加
特に40歳以下の世代では、オンライン診療利用者が全体の約75%を占めており、デジタルネイティブ世代の医療ニーズに合致しています。
引用元:総務省「令和3年版情報通信白書」
医療DX推進による政府政策の後押し
政府の医療DX推進政策が市場成長を強力にサポートしています。
政府は「規制改革実施計画」においてオンライン診療を重点分野に位置づけ、2030年までの全国普及を目標に掲げています。
具体的な政策支援として以下の取り組みが実施されています。
- 補助金制度: IT導入補助金でシステム導入費用を支援
- 人材育成: オンライン診療研修の義務化と標準化
- 基盤整備: 電子処方箋システムとの連携強化
- 規制緩和: 診療報酬の段階的改善と要件緩和
政府は医療費抑制と地域医療格差解消の観点から、オンライン診療普及により年間医療費を5-10%削減する目標を設定しています。
この政策的後押しにより、医療機関にとって導入のメリットが明確化され、積極的な取り組みが促進されています。
オンライン診療システムを開発・提供している主要企業
オンライン診療システム市場では、多様な企業が競争を展開しています。
既存の医療IT企業から大手IT企業、新興ヘルステック企業まで幅広いプレイヤーが参入し、激しい競争が繰り広げられています。
主要企業の動向と市場シェアについて詳しく解説しているので、ぜひ読んでみましょう。
メドレー(CLINICS)の市場シェアと特徴
株式会社メドレーが提供する「CLINICSオンライン診療」は、国内市場で最大のシェアを誇る代表的なサービスです。
2021年の実績で導入実績No.1を獲得し、全国約3,300の医療機関で利用されています。
| サービス名 | 提供企業 | 特徴 | 導入実績 |
|---|---|---|---|
| CLINICSオンライン診療 | メドレー | 予約〜決済まで一体型 | 約3,300件 |
| ポケットドクター | MRT | 医師間連携機能 | 約1,500件 |
| CARADA オンライン診療 | カラダメディカ | 女性向け特化 | 約1,000件 |
CLINICSの強みは、オンライン診療に特化した包括的なサービスを提供している点です。
単なるビデオ通話機能だけでなく、予約管理、電子カルテ連携、決済処理、処方薬配送まで一気通貫でサポートしています。
引用元:富士キメラ総研「ウェアラブル/ヘルスケアビジネス総調査 2023」
MICIN・カラダメディカなど新興企業の動向
新興ヘルステック企業も積極的に市場参入を進めています。
特に注目されるのが、MICIN株式会社とカラダメディカ株式会社です。
MICINは「oVice」を活用したバーチャル空間での診療システムを開発し、次世代型オンライン診療として注目を集めています。
カラダメディカは、エムティーアイ(9438)とメディパルホールディングス(7459)の合弁会社として設立され、「CARADA オンライン診療」と「ルナルナ オンライン診療」を運営しています。
・CARADA オンライン診療: 一般的なオンライン診療サービス
・ルナルナ オンライン診療: 女性特有の健康課題に特化
女性向け特化サービスでは、基礎体温データや生理周期情報を活用したより精密な診療が可能となっており、産婦人科領域で高い評価を得ています。
引用元:ダイヤモンド・ザイ「オンライン診療関連銘柄の7社を紹介」
大手IT企業の参入状況と競争激化
大手IT企業の市場参入により、競争が激化しています。
LINEヘルスケア株式会社は「LINEドクター」を提供し、日常使いのLINEアプリを通じてオンライン診療を受けられるサービスを展開しています。
・LINE ドクター: LINEアプリ上で完結するサービス
・健康相談サービス: 累計30万件の相談実績
・初期費用無料: 医療機関の導入ハードルを大幅に削減
また、富士通株式会社も「HOPE LifeMark-コンシェルジュ」として本格参入し、家族登録機能など独自の付加価値を提供しています。
エムスリー(2413)は、医療従事者向けサイト「m3.com」で培ったネットワークを活用し、LINEと提携してサービス拡大を図っています。
この大手企業の参入により、価格競争と機能競争が同時に進行し、医療機関にとってはより良いサービスを選択できる環境が整っています。
クリニック向けオンライン診療導入の活用事例
オンライン診療導入の成功事例を通じて、実際の効果と課題が明確になってきています。
地方から都市部まで、診療科を問わず多様な活用パターンが確立され、それぞれに特徴的な成果を上げています。
具体的な活用事例について詳しく解説しているので、ぜひ読んでみましょう。
地方クリニックでの患者アクセス改善効果
地方クリニックでは、患者の通院負担軽減において顕著な効果を上げています。
千葉県いすみ市の小児科クリニックでは、小児科専門医が50km圏内にいない地域でオンライン診療を導入し、大幅な患者アクセス改善を実現しました。
導入前後の変化は以下の通りです。
・通院患者数: 月間150名 → 200名(33%増加)
・継続治療率: 65% → 85%(20ポイント向上)
・患者満足度: 72% → 91%(19ポイント向上)
特に効果的だったのは、急性期症状の早期対応です。
従来は「様子を見る」しかなかった軽微な症状に対して、オンライン診療により早期介入が可能となり、重症化防止につながりました。
引用元:リクルートドクターズキャリア「オンライン診療の現状とこれから」
都市部での効率化と患者満足度向上事例
都市部のクリニックでは、効率化と患者満足度向上の両立を実現しています。
東京都内の内科・呼吸器内科クリニックでは、オンライン診療導入により以下の成果を得ました。
- 待ち時間の大幅短縮: 平均45分 → 10分以下
- 診療効率の向上: 1日あたり診療患者数20%増加
- 院内感染リスク低減: 発熱患者の院内滞在時間90%削減
産婦人科クリニックでは、妊婦健診の一部をオンライン化することで、つわりで通院困難な妊婦への継続的なケアを実現しています。
・妊婦の通院回数: 14回 → 10回(対面)+ 4回(オンライン) ・妊婦の負担軽減: 交通費・時間コスト月平均8,000円削減 ・継続受診率: 93% → 98%(5ポイント向上)
診療科別の導入成功パターン分析
診療科別の導入パターンを分析すると、それぞれの専門性に応じた活用方法が確立されています。
| 診療科 | 主な活用場面 | 導入効果 | 成功要因 |
|---|---|---|---|
| 内科 | 慢性疾患管理 | 継続受診率向上 | 定期的なモニタリング |
| 精神科 | カウンセリング | 受診ハードル低減 | プライバシー保護 |
| 皮膚科 | 経過観察 | 早期治療介入 | 画像による状態確認 |
| 小児科 | 急性症状対応 | 重症化防止 | 保護者の安心感 |
特に慢性疾患管理において効果が顕著で、高血圧・糖尿病・高脂血症などの生活習慣病では、オンライン診療により治療継続率が15-20%向上しています。
精神科・心療内科では、受診への心理的ハードルが大幅に低下し、従来受診を控えていた患者層の掘り起こしに成功しています。
オンライン診療を利用した精神科患者の約80%が対面診療よりも話しやすいと回答しており、治療効果の向上も報告されています。
まとめ【クリニック向けオンライン診療導入市場の将来展望】
クリニック向けオンライン診療導入市場は、新型コロナウイルス感染症を契機として急速に拡大し、今後も継続的な成長が見込まれています。
市場規模は2020年の約32億円から2035年には106億円超への成長が予測され、クリニックの導入率も15.2%から更なる上昇が期待されます。
成功要因として、政府の医療DX推進政策、診療報酬制度の段階的改善、患者ニーズの変化が挙げられ、これらの追い風により市場環境は着実に改善しています。
主要企業間の競争激化により、システムの機能向上と価格競争が進み、クリニックにとってより導入しやすい環境が整っています。
実際の導入事例からは、地方での患者アクセス改善、都市部での効率化、診療科別の専門的活用など、多様な成功パターンが確立されていることが分かります。
今後は、AIやIoT技術との融合により、より高度な診療支援機能の実装が進み、オンライン診療の質的向上と適用範囲の拡大が期待されます。クリニック経営者にとって、オンライン診療導入は競争力強化の重要な戦略選択肢となっているのが現状です。
参考URL:
- 総務省「令和3年版情報通信白書」: https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd122320.html
- 富士経済「2022年 医療連携・医療プラットフォーム関連市場の現状と将来展望」: https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=22007&view_type=2&la=ja
- 厚生労働省「オンライン診療について」: https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html
- CLINICS「オンライン診療のシェア状況をデータで徹底解説」: https://clinics-cloud.com/column/276
- マイナビDOCTOR「オンライン診療の普及率は?」: https://doctor.mynavi.jp/column/online_medical_treatment