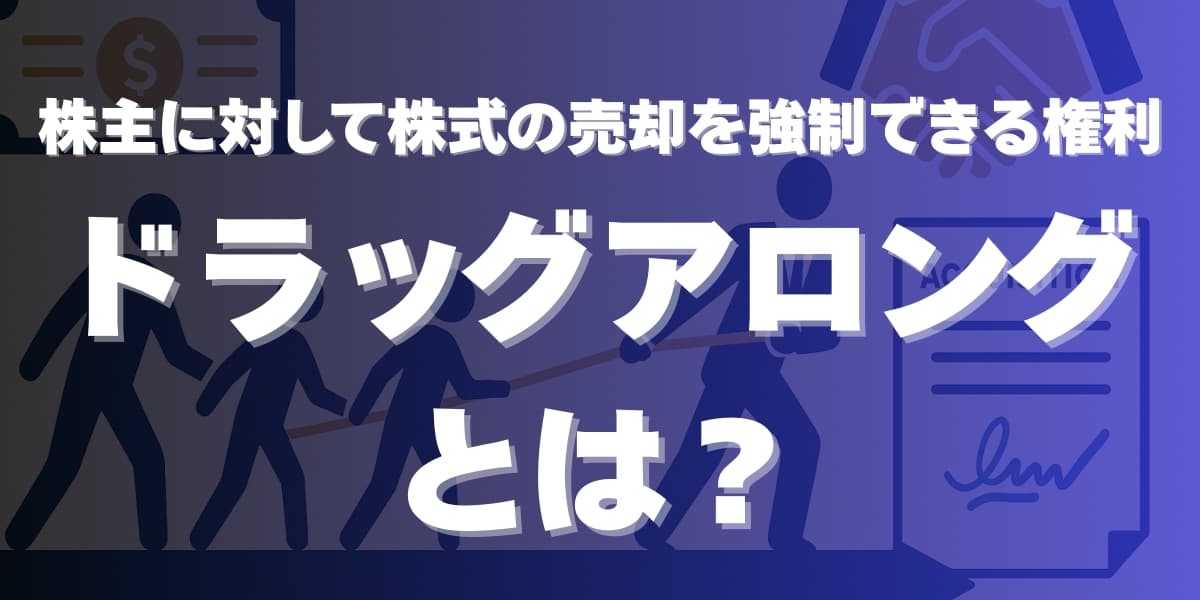「投資契約書にドラッグアロングという条項があるけど、どういう意味なの?」「強制売却権って聞くと不安になるが、実際にはどのような仕組みなのだろう?」「タグアロングとの違いがよく分からない」
このような疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
ドラッグアロングとは、M&A契約や株主間契約において規定される強制売却権のことで、一定の要件を満たした場合に他の株主に対して株式の売却を強制できる権利です。
本記事では、ドラッグアロングの基本的な仕組みから実際の活用事例まで分かりやすく解説します。
理解することで投資契約の内容を適切に判断でき、今後のM&A戦略やイグジット計画の策定にも役立てることができます。
この記事で分かること
ドラッグアロングの基本的な仕組みと法的位置づけ
タグアロングとの違いと使い分けのポイント
実際の企業での活用事例と導入時の注意点
分かりやすく解説しているので、ぜひお読みください。
目次
ドラッグアロングとは?投資家向け解説
ドラッグアロングの基本的な仕組み
ドラッグアロングとは、株式売却に関する強制売却権を意味する法的権利です。
英語の「Drag Along」を直訳すると「引きずって連れて行く」という意味で、まさにその名の通り他の株主を巻き込んで売却を強制する仕組みです。
具体的には、一定の要件を満たした株主が第三者に株式を売却する際、他の株主に対しても同じ条件で売却するよう強制できる権利を指します。
例えば、ベンチャー企業でVC(ベンチャーキャピタル)が60%、創業者が40%の株式を保有している場合を考えてみましょう。
VCがM&Aによる売却を決定した際、創業者が反対したとしても、ドラッグアロング権により創業者の株式も一緒に売却を強制できます。
ドラッグアロング権が発生する背景
実は、ドラッグアロングが必要になる背景には、M&A取引の実務的な課題があります。
M&A買収では、買い手企業が経営権の完全な取得を目指すケースがほとんどです。
しかし、少数株主が株式売却を拒否すると、買い手企業は100%の株式取得ができなくなります。
具体例として、買い手企業が「100%株式取得でなければ買収しない」と条件を出した場合、1%の株式を持つ株主が反対するだけで、数十億円規模のM&A取引が破談になる可能性があります。
このような事態を防ぐため、投資契約の段階でドラッグアロング条項を設定し、スムーズなM&A実行を可能にしています。
法的な位置づけと強制売却権の特徴
ドラッグアロング権は、M&A契約書や株主間契約書において明文化される契約上の権利です。
一般的には「強制売却権」「売却請求権」「売渡請求権」などの名称で呼ばれることもあります。
重要なポイントは、この権利が株主間の合意に基づいて成立することです。
つまり、株主になる段階でドラッグアロング条項に同意しているため、後から「知らなかった」という主張は通用しません。
法的な強制力を持つ一方で、発動には一定の要件が必要であり、投資家の気分次第で自由に行使できるものではない点も特徴的です。
これまでの株主間契約との違い
従来の株主間契約の課題点
従来の株主間契約では、ドラッグアロングのような強制的な売却権限は存在しませんでした。
そのため、M&A実行時に少数株主が反対すると、交渉が長期化したり取引が破談になったりするリスクが常に存在していました。
具体的には、全株主の個別同意が必要となり、1人でも反対者がいれば100%株式譲渡が実現できない状況でした。
例えば、10人の株主がいる企業で9人が売却に賛成しても、1人が反対すれば買い手企業が買収を断念するケースが頻発していました。
特に親族経営の中小企業では、感情的な対立により合理的な判断が困難になる場面も多く見られました。
ドラッグアロングによる解決効果
ドラッグアロング条項の導入により、これらの課題が劇的に改善されました。
一定の要件を満たせば、反対する株主がいても強制的に売却を実行できるため、M&A取引の確実性が大幅に向上しています。
投資家にとっては、投資回収の確実性が高まり、より積極的な投資判断が可能になりました。
企業側にとっても、M&A交渉において「全株主の同意が得られる」という確約を買い手に提供できるため、より有利な条件での売却が期待できます。
実際に、ドラッグアロング権を設定している企業の方が、M&A市場での評価が高くなる傾向が見られています。
少数株主保護との関係性
意外にも、ドラッグアロングは少数株主にとってもメリットがある仕組みです。
なぜなら、大株主と全く同じ条件で株式を売却できるため、不利な条件で売却を強要されることがないからです。
従来の株主間契約では、少数株主が個別に売却交渉を行う必要があり、大株主より不利な条件になることも珍しくありませんでした。
ドラッグアロング権の行使時は、株式の売却価格や条件が全株主で統一されるため、公平性が確保されています。
ただし、売却のタイミングを自分で決められないという制約があるため、タグアロングと組み合わせて設定するケースが一般的です。
ドラッグアロングが注目される理由
ベンチャー投資市場の拡大背景
日本のベンチャー投資市場は、実は欧米ほど大きな冷え込みを見せていません。
2023年のスタートアップによる資金調達額は7536億円で、前年比12%減となったものの、欧米のように投資額が約半減するほどの市況の影響は受けていません。
この背景には、ドラッグアロングのような投資保護条項が普及し、投資家の安心感が高まっていることがあります。
特に注目すべきは、優良なスタートアップは50億円から100億円規模の大型資金調達を実現できている点です。
これらの大型調達案件では、ドラッグアロング条項がほぼ標準的に設定されており、投資家の資金回収リスクを軽減しています。
M&Aによるイグジット戦略の重要性
実は、IPO市場の低迷により、M&Aによるイグジットの重要性が急激に高まっています。
IPO市場の低迷により、グロースステージのスタートアップはIPO時期を2、3年後ろ倒しにする傾向が顕著になっている状況です。
このような環境下で、ドラッグアロング権はM&Aによる確実な資金回収を可能にする重要な仕組みとなっています。
従来であればIPOを目指していた企業も、M&A戦略に軸足を移すケースが増えており、買い手企業は100%株式取得を前提とした買収を求める傾向が強まっています。
ドラッグアロング条項があることで、売り手企業は「全株主の同意を得られる」という確約を買い手に提供でき、より有利な売却交渉が可能になります。
投資家の資金回収ニーズの高まり
意外にも、ベンチャー投資の長期化傾向がドラッグアロングへの注目を高めています。
一般的にベンチャー投資のファンド期間は10年程度ですが、IPO環境の悪化により投資回収期間が長期化する傾向にあります。
このような状況で、投資家は確実な資金回収手段としてドラッグアロング権の重要性を再認識しています。
特に機関投資家やファンドは、投資先への出資者に対する説明責任があるため、不確実性の高いIPOよりも、条件次第で確実に実行できるM&Aによる回収を重視する傾向が強まっています。
実際に、投資契約におけるドラッグアロング条項の発動要件も、従来より柔軟に設定されるケースが増えており、投資家の資金回収機会の確保が重要視されています。
ドラッグアロングを開発・提供している主要企業
ベンチャーキャピタルでのドラッグアロング活用事例
日本の主要ベンチャーキャピタルでは、ドラッグアロング条項が投資契約の標準的な項目として定着しています。
特に金融機関系VCでは、三菱UFJキャピタルやみずほキャピタルなど、大手金融機関をバックボーンとするVCが積極的にドラッグアロング権を投資条件に盛り込んでいます。
独立系VCにおいても、グロービス・キャピタル・パートナーズやジャフコなど、実績豊富なVCが投資先の確実なイグジット実現のためドラッグアロング条項を重視しています。
実は、米国シリコンバレーではドラッグアロングが一般的な条項として普及していましたが、日本では比較的新しい概念でした。
しかし、近年のIPO環境の変化により、日本のVCもドラッグアロング権の重要性を再認識し、投資契約における必須項目として位置づけるようになっています。
スタートアップ企業でのドラッグアロング導入実績
実際にドラッグアロング条項を導入しているスタートアップ企業では、資金調達時の投資家との交渉がスムーズに進む傾向があります。
特にシリーズA以降の資金調達では、投資家側からドラッグアロング権の設定を求められるケースが増えており、事前に条項を整備している企業は競争優位性を持てます。
意外にも、ドラッグアロング条項の導入は創業者にとってもメリットがあることが実証されています。
例えば、複数の投資家が参画している企業では、M&A時の株主間調整が複雑化する傾向にありますが、ドラッグアロング権があることで迅速な意思決定が可能になります。
また、条項の存在により買い手企業に対して「確実に100%株式取得が可能」という安心感を提供でき、結果として高い企業評価を得られる場合も多く報告されています。
法律事務所でのドラッグアロング契約書作成サポート
ドラッグアロング条項の作成には高度な法的専門知識が必要なため、多くの企業が法律事務所のサポートを受けています。
TMI総合法律事務所やAZX、モノリス法律事務所など、ベンチャー法務に特化した法律事務所ではドラッグアロングに関する豊富なノウハウを蓄積しています。
これらの法律事務所では、単純な条項作成だけでなく、発動要件の設定や少数株主への配慮事項についても包括的なアドバイスを提供しています。
特に注目すべきは、ドラッグアロング条項について理解している法律専門家が限られているという現実です。
そのため、ベンチャー法務に精通した弁護士との連携が、適切なドラッグアロング権の設計には不可欠となっています。
ドラッグアロングの活用事例
IPO前企業でのドラッグアロングによるM&A促進事例
IPO申請を予定していた企業がドラッグアロング条項を活用してM&Aに切り替える事例が増加しています。
典型的なケースでは、IPO準備中の企業に予想以上の高額買収提案があった場合、ドラッグアロング権の発動により迅速なM&A実行が可能になります。
実際に、ある条項例では「○年○月○日までにIPOを申請していない場合」や「○億円以上の買収の申し入れがあった場合」が発動要件として設定されています。
この仕組みにより、投資家は確実な資金回収機会を確保でき、企業側も市場環境に応じた柔軟な戦略変更が可能になります。
特に注目すべきは、ドラッグアロング条項の存在により、買い手企業が100%株式取得を前提とした積極的な買収提案を行いやすくなることです。
投資家主導によるドラッグアロング強制売却実例
ベンチャー投資において、投資家がドラッグアロング権を行使した具体的な事例が報告されています。
例えば、10%の株式を保有するVCが、残り90%を持つ経営陣に対してドラッグアロング権を発動し、全株式を第三者企業に売却した事例があります。
この場合、VCは自身の持分だけでは売却が困難でしたが、ドラッグアロング条項により経営陣の株式も含めた完全な株式譲渡を実現しました。
重要なポイントは、少数株主でもドラッグアロング権を持つことで、M&A交渉における発言力を確保できることです。
ただし、このような権利行使は投資契約で事前に合意された発動要件を満たした場合のみに限定されており、投資家の一方的な判断では実行できません。
タグアロングとの併用によるドラッグアロング株主保護事例
実務では、ドラッグアロングとタグアロングを併用することで、より公平な株主保護を実現している事例が多く見られます。
タグアロング権により少数株主は大株主の売却に任意で参加でき、ドラッグアロング権により必要な場合は強制的な売却も可能になります。
この組み合わせにより、少数株主は「売却に参加する権利」と「売却を強制される義務」の両方を持つことになります。
具体的な事例では、創業者が30%、複数の投資家がそれぞれ10-20%を保有する企業で、いずれかの大株主が売却を決定した際に、他の株主全員が同条件で売却参加できる仕組みが構築されています。
この方式は、株主間の利害調整を効率的に行いながら、M&A取引の確実性も確保できる優れた手法として注目されています。
まとめ【ドラッグアロングの重要性と今後の展望】
ドラッグアロングは、M&A契約や株主間契約において規定される強制売却権として、現代のベンチャー投資において重要な役割を果たしています。
従来の株主間契約では実現困難だった確実なM&A実行を可能にし、投資家の資金回収リスクを大幅に軽減する仕組みとして機能しています。
特に注目すべきは、IPO市場の低迷により M&Aによるイグジット戦略の重要性が高まっている現在の市場環境において、ドラッグアロング権が果たす役割の大きさです。
ベンチャーキャピタルや法律事務所などの専門機関では、ドラッグアロング条項の設計と運用に関するノウハウが蓄積されており、適切な契約書作成サポートが提供されています。
実際の活用事例からも明らかなように、ドラッグアロングは大株主だけでなく少数株主にとってもメリットのある仕組みとして機能しており、公平な条件での株式売却機会を提供しています。
今後も日本のベンチャー投資市場の成熟とともに、ドラッグアロングの重要性はさらに高まっていくと考えられます。
参考URL:
- https://www.marr.jp/yougo/detail/145
- https://www.komon-lawyer.jp/column/venture/column57/
- https://madx.co.jp/manda_souzoku_daigaku/jigyoshokei_gakubu/tag-along-right/
- https://masouken.com/タグアロングとは
- https://www.azx.co.jp/blog/8030
- https://www.startuplist.jp/alliance_posts/77
- https://ma-bank.jp/reading/1_03/