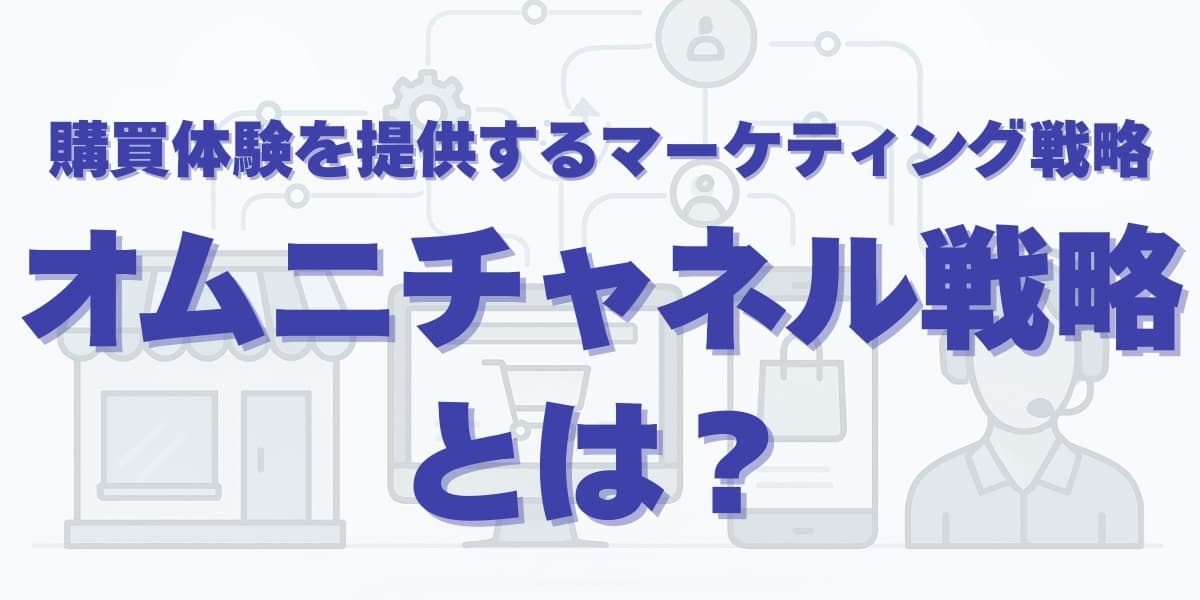「オムニチャネル戦略って何のこと?」
「マルチチャネルとは何が違うの?」
「実際にどんな効果があるの?」
このような疑問を持つ方は多いのではないでしょうか?
オムニチャネル戦略とは、実店舗・ECサイト・アプリなど複数の販売チャネルを統合し、顧客がどの接点からでもシームレスな購買体験を提供するマーケティング戦略です。
単純に複数のチャネルを持つマルチチャネルとは異なり、全てのチャネルで顧客データや在庫情報を共有し、一貫したサービスを実現します。
本記事では、オムニチャネル戦略の基本的な仕組みから具体的な企業事例まで分かりやすく解説します。
理解することで、現代の消費者ニーズに対応した効果的な販売戦略の構築が可能になり、今後のビジネスチャンスも見えてくるでしょう。
この記事で分かること
・オムニチャネル戦略の基本的な仕組みと特徴
・従来のマルチチャネル戦略との明確な違い
・ユニクロやイオンなど成功企業の具体的事例
分かりやすく解説しているので、ぜひお読みください。
目次
オムニチャネル戦略とは?基本的な仕組み解説
オムニチャネル戦略は、実は2010年代から本格的に注目され始めたマーケティング手法です。
従来のマルチチャネル戦略とは異なり、各チャネルのデータを統合し、顧客中心のシームレスなサービスを実現する点が最大の特徴です。
オムニチャネル戦略の基本定義と特徴
オムニチャネル戦略とは、企業が持つ全ての販売チャネルを統合し、顧客にシームレスな購買体験を提供する戦略です。
「オムニ(Omni)」は「すべて」という意味で、「チャネル(Channel)」は顧客との接点を指します。
実は、オムニチャネルの概念は1990年代のアメリカで生まれており、決して新しいものではありません。
しかし、スマートフォンの普及とデジタル技術の進歩により、近年になって本格的な導入が可能になりました。
具体的には、実店舗・ECサイト・モバイルアプリ・SNS・コールセンターなど、あらゆる顧客接点で一貫した情報とサービスを提供します。
例えば、ECサイトで商品を閲覧した顧客が、実店舗で同じ商品を試着し、最終的にアプリで購入するといった体験が可能です。
チャネル統合による顧客体験の変化
従来の販売方法では、各チャネルが独立して運営されていました。
そのため、「実店舗で見た商品がECサイトで見つからない」「ポイントがチャネル間で共有されない」といった課題がありました。
オムニチャネル戦略では、これらの課題を解決し、顧客中心の体験を実現します。
例えば、店舗で在庫切れの商品を店員がその場でECサイトから注文し、顧客の自宅に配送することが可能です。
また、どのチャネルで購入してもポイントが統一され、顧客情報も一元管理されます。
このような統合により、顧客は「企業」として一貫したサービスを受けられるようになります。
オムニチャネル戦略の具体的な仕組み
オムニチャネル戦略の実現には、技術的な基盤整備が不可欠です。
最も重要なのは、顧客情報・商品情報・在庫情報の一元管理システムです。
具体的には、CRM(顧客管理)システム・ERP(基幹業務)システム・POS(販売時点)システムの連携が必要になります。
例えば、顧客がアプリで商品を「お気に入り」に登録すると、実店舗のスタッフもその情報を確認でき、来店時に最適な提案が可能になります。
また、リアルタイムの在庫連携により、「店舗で確認→ECで購入→別店舗で受取」といった柔軟な購買体験を提供できます。
さらに、各チャネルでの顧客行動データを統合分析することで、より精度の高いマーケティングも実現します。
これまでのマルチチャネル戦略との違い
オムニチャネル戦略とマルチチャネル戦略の違いは、データ統合の有無にあります。
オムニチャネル戦略では、全チャネルのデータが統合され、どの接点からでも一貫したサービスを受けられる環境を構築します。
マルチチャネル戦略の限界と課題
マルチチャネル戦略は、複数の販売チャネルを並行して運営する従来の手法です。
一般的には効果的な戦略と思われがちですが、実際には大きな限界がありました。
最大の課題は、各チャネルが独立して機能するため、顧客データや在庫情報が分断されることです。
例えば、実店舗で購入した履歴がECサイトに反映されず、顧客は同じ情報を何度も入力する必要がありました。
また、チャネル間で価格や在庫状況が異なるため、顧客が混乱するケースも頻発していました。
さらに、各部門が独自の目標を持つため、チャネル間で売上の奪い合いが発生することもありました。
オムニチャネル戦略の進化したポイント
オムニチャネル戦略は、マルチチャネルの課題を根本から解決する進化した手法です。
最大の違いは、全チャネルのデータが統合され、「ひとつの企業」として一貫したサービスを提供する点です。
具体的には、どのチャネルで商品を購入しても、顧客の購買履歴や好みが全て記録されます。
例えば、ECサイトで閲覧した商品を実店舗で試着し、最終的にアプリで購入した場合でも、全ての行動が一連の購買プロセスとして管理されます。
また、在庫も全チャネルで共有されるため、「店舗では売り切れでもECサイトには在庫がある」といった状況を解消できます。
このような統合により、顧客満足度の向上と企業の効率化を同時に実現します。
クロスチャネル戦略との差別化要因
マルチチャネルとオムニチャネルの中間に位置するのが、クロスチャネル戦略です。
クロスチャネルでは、チャネル間でデータを部分的に連携させる取り組みが行われます。
しかし、完全なシームレス体験の提供までは実現できていません。
例えば、ECサイトで購入した商品を店舗で受け取ることはできても、店舗スタッフが顧客のオンライン行動履歴を把握できない場合があります。
オムニチャネル戦略では、こうした制限を完全に取り除き、全てのチャネルが有機的に連携します。
顧客がどのチャネルを利用しても、企業側は過去の全ての接触履歴を把握し、最適なサービスを提供できるのが最大の特徴です。
オムニチャネル戦略が注目される理由
オムニチャネル戦略への注目は、消費者行動の劇的な変化が背景にあります。
スマートフォンの普及により、顧客は24時間いつでもどこでも商品情報にアクセスできるようになりました。
デジタル化による消費行動の多様化
現代の消費者行動は、実に複雑で多様化しています。
スマートフォンの普及により、顧客は24時間いつでもどこでも商品情報にアクセスできるようになりました。
例えば、通勤中にSNSで商品を発見し、昼休みにECサイトで詳細を確認し、帰宅途中に実店舗で実物をチェックするといった行動が日常的になっています。
オムニチャネル戦略は、このような複雑な顧客行動に対応する必要性から注目されました。
従来のような単一チャネル中心のアプローチでは、顧客の多様なニーズを満たすことが困難になったのです。
また、新型コロナウイルスの影響により、オンラインとオフラインを使い分ける消費行動がさらに加速しています。
顧客満足度向上と売上拡大の両立
オムニチャネル戦略が注目される最大の理由は、顧客満足度と企業利益を同時に向上させる効果にあります。
実際に、ECと店舗を併用する顧客の年間購入額は、単一チャネル利用者の約3倍になるというデータがあります。
これは、顧客にとって利便性が高く、企業にとっても収益機会の拡大につながることを意味します。
例えば、ECサイトで購入した商品を店舗で受け取る際に、顧客が追加の商品を購入するケースが増加しています。
また、店舗スタッフが顧客のオンライン購買履歴を把握することで、より的確な商品提案が可能になります。
このような相乗効果により、顧客満足度と売上の両方を向上させることができます。
アメリカ発祥から日本企業への浸透
オムニチャネル戦略の発端は、2011年にアメリカの百貨店Macy’s(メイシーズ)が宣言したことから始まりました。
ECの普及により店舗売上が低迷していたMacy’sは、実店舗とECサイトの統合に取り組みました。
その結果、翌年には在庫を40%以上圧縮し、大幅な業績回復を実現しています。
この成功事例が世界中で注目され、日本でも大手企業が相次いで導入を開始しました。
現在では、小売業だけでなく金融業界でもオムニチャネル戦略の導入が進んでいます。
日本企業の場合、アメリカと比較するとまだ発展の余地があり、今後さらなる普及が期待されています。
オムニチャネル戦略を推進している主要企業
オムニチャネル戦略を積極的に推進している企業は、業界を問わず成果を上げています。
小売業界では、ユニクロやイオンが代表的な成功事例として知られています。
ユニクロの革新的なアプリ連携事例
ユニクロは、日本におけるオムニチャネル戦略の代表的な成功事例として知られています。
同社のアプリ会員数は、2021年8月時点で国内5,700万人、グローバルでは1.4億人に達しています。
特に注目すべきは、「UNIQLO IQ」と呼ばれるAIチャットボットによる接客サービスです。
顧客はアプリを通じて気軽にコーディネートを相談し、商品の在庫確認やオンライン購入ができます。
また、ECサイトで購入した商品を店舗で受け取ると送料が無料になる仕組みにより、実店舗への送客も実現しています。
実際に、ECと店舗を併用する顧客の年間購入額は、単一チャネル利用者を大幅に上回る結果が出ています。
イオングループの統合プラットフォーム
イオングループでは、「AEON.com(イオンドットコム)」を中心としたオムニチャネル戦略を展開しています。
このプラットフォームは、グループ全体の商品を横断的に閲覧・購入できる統合サイトとして機能しています。
特徴的なのは、スマートフォンアプリの「撮って!インフォ」機能です。
店内の商品POPやチラシを読み込むと、関連するレシピが提案され、必要な食材をそのまま購入できます。
また、店頭で取り扱いのない商品をECで検索し、店舗のレジで支払って自宅に配送するサービスも提供しています。
2022年2月期のデジタル売上高は1,300億円となり、2020年2月期の700億円から2年で約2倍に成長しています。
りそなホールディングスの金融DX
金融業界でもオムニチャネル戦略の導入が進んでおり、りそなホールディングスがその先駆者として知られています。
2016年から「りそなのオムニチャネル宣言」を掲げ、デジタル化を積極的に推進してきました。
「りそなグループアプリ」は2019年に100万ダウンロードを突破し、口座残高確認や支出分析機能を提供しています。
AIが口座状況や銀行取引を分析し、無駄な出費や貯金についてアドバイスする機能も搭載されています。
また、顧客がタブレットを操作して事務手続きを完結させたり、テレビ窓口で専門スタッフが対応したりする仕組みも導入しています。
このような取り組みにより、顧客満足度の向上と店舗の負担軽減を同時に実現しています。
オムニチャネル戦略の成功活用事例
オムニチャネル戦略の成功事例は、在庫統合と顧客体験の向上に集約されます。
このような取り組みにより、販売機会の拡大と顧客満足度の向上を同時に実現している企業が増加しています。
小売業界での在庫統合による効果
オムニチャネル戦略の最も分かりやすい成功事例は、在庫統合による販売機会の拡大です。
従来の小売業では、実店舗とECサイトで別々に在庫を管理していました。
その結果、「店舗では売り切れだが、ECサイトには在庫がある」という機会損失が頻繁に発生していました。
無印良品では、「MUJI passport」アプリを通じて全チャネルの在庫情報を統合しています。
顧客は店舗にいながらオンラインの在庫を確認し、その場で取り寄せや配送の手配ができます。
また、購入や来店でポイントが貯まる仕組みにより、オンラインとオフラインの相互送客も実現しています。
アプリを活用した顧客エンゲージメント
オムニチャネル戦略において、スマートフォンアプリは顧客との接点強化に重要な役割を果たしています。
ビックカメラでは、公式アプリの刷新により200以上の実店舗とECサイトを連携させています。
顧客はアプリで商品の価格比較や在庫確認を行い、最適な購入方法を選択できます。
また、店舗で商品のバーコードをスキャンすると、オンラインのレビューや関連商品情報が即座に表示されます。
このような機能により、リアルとデジタルが融合した新しい買い物体験を提供しています。
アプリを通じた顧客データの収集により、よりパーソナライズされたマーケティングも可能になっています。
店舗受取サービスの相乗効果
ECサイトで購入した商品を実店舗で受け取る「店舗受取サービス」は、オムニチャネル戦略の代表的な施策です。
このサービスの効果は、単なる送料削減にとどまりません。
イオングループのコックスでは、店舗受取がEC売上の1割以上を占め、利用件数が前年比130%以上に伸長しています。
重要なのは、商品受取に来店した顧客の約30%が追加で商品を購入することです。
これは、顧客が店舗を訪れる機会を創出し、新たな販売機会につなげる効果を示しています。
また、店舗スタッフが顧客のオンライン購買履歴を把握することで、より的確な商品提案も可能になっています。
まとめ【オムニチャネル戦略の将来性と企業価値】
オムニチャネル戦略は、複数の販売チャネルを統合し、顧客にシームレスな購買体験を提供する現代的なマーケティング手法です。
従来のマルチチャネル戦略とは異なり、全てのチャネルでデータを共有し、一貫したサービスを実現する点が特徴です。
スマートフォンの普及とデジタル技術の進歩により、消費者行動が多様化したことが注目される主な背景となっています。
ユニクロやイオン、りそなホールディングスなどの成功事例では、顧客満足度の向上と売上拡大を同時に実現していることが確認できます。
特に、ECと店舗を併用する顧客の購買額が単一チャネル利用者を大幅に上回る傾向は、この戦略の有効性を示しています。
在庫統合による販売機会の拡大、アプリを通じた顧客エンゲージメントの強化、店舗受取サービスによる相乗効果など、具体的な成果も多数報告されています。
オムニチャネル戦略は、今後も消費者ニーズの多様化に対応する重要な手法として、様々な業界での展開が期待されます。