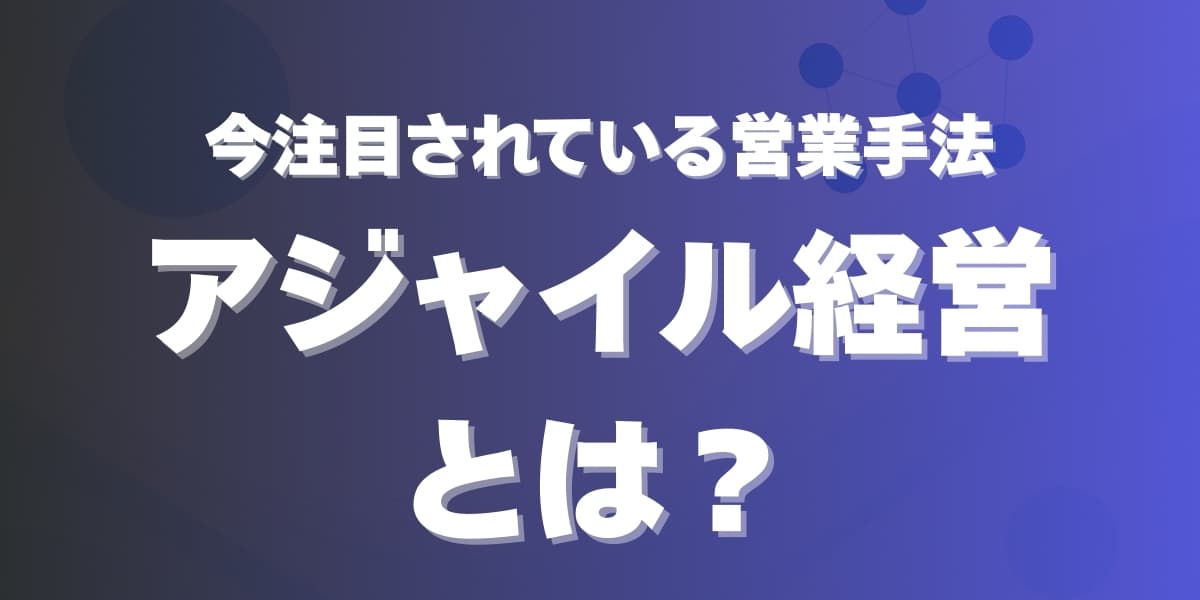「アジャイル経営という言葉をよく聞くけれど、実際にはどのような経営手法なのか分からない」「従来の経営手法と何が違うのかが理解できない」「なぜ今アジャイル経営が注目されているのか知りたい」
このような疑問を持つ方は多いのではないでしょうか?
アジャイル経営とは、変化の激しい現代において、企業が市場や顧客ニーズの変化に迅速に対応できる組織運営手法です。
本記事では、アジャイル経営の基本的な仕組みから従来の経営手法との違い、注目される理由まで分かりやすく解説します。
理解することで、自社の組織運営を見直すきっかけとなり、今後の激しい市場競争を勝ち抜くための重要な知識を得ることができるでしょう。
この記事で分かること
・アジャイル経営の基本概念と仕組み
・従来のウォーターフォール経営との根本的な違い
・企業がアジャイル経営を導入する具体的な方法と事例
分かりやすく解説しているので、ぜひお読みください。
目次
アジャイル経営とは?基本的な仕組み解説
アジャイル経営は、変化への迅速な対応を最優先とする組織運営手法です。
従来の長期計画に基づく経営とは根本的に異なり、短期間での実行と改善を繰り返しながら事業を推進します。
実は、この手法は日本企業にとって決して新しい概念ではありません。
アジャイル経営の基本定義と特徴
アジャイル経営とは、「機敏で素早い」という意味のアジャイル(Agile)を経営に応用した手法です。
具体的には、3~10人程度の小規模チームが自律的に判断し、短期間で計画・実行・検証のサイクルを回します。
一般的には長期計画を重視する経営が主流と思われがちですが、アジャイル経営では「計画よりも変化への対応」を優先します。
例えば、新商品開発において従来なら1年かけて完成品を作りますが、アジャイル経営では1カ月で試作品を作り顧客の反応を確認します。
その反応をもとに改良を重ね、最終的により顧客ニーズに合った商品を短期間で市場投入できるのが特徴です。
ソフトウェア開発から生まれた経営手法
アジャイル経営の起源は、実は2001年にアメリカで生まれた「アジャイルソフトウェア開発宣言」にあります。
当時のソフトウェア開発では、詳細な設計書を作成してから開発を始める「ウォーターフォール開発」が主流でした。
しかし、開発期間が長期化し、完成時には顧客のニーズが変化してしまう問題が頻発していました。
そこで17名の開発者が「個人と対話を重視」「動くソフトウェアを優先」「顧客との協調を大切に」「変化への対応を重要視」という4つの価値観を掲げました。
この考え方が経営分野に応用され、現在のアジャイル経営として発展したのです。
スクラムを活用した組織運営の仕組み
アジャイル経営の実践において中核となるのが「スクラム」と呼ばれる組織運営の仕組みです。
スクラムとは、ラグビーで選手が肩を組み合う陣形から名付けられた、職種を横断した小規模チームのことです。
例えば、営業・マーケティング・開発・財務など異なる部門から1名ずつ選出し、4~7名程度のチームを編成します。
このチームには明確な権限と責任が与えられ、上司の承認を得ることなく自律的に意思決定を行います。
重要なのは、チームメンバー全員が対等な立場で議論し、全員が納得した結論に基づいて行動することです。
意外にも、このスクラムという概念は1986年に日本の製品開発手法を研究した論文が起源となっています。
これまでのウォーターフォール経営との違い
アジャイル経営と従来のウォーターフォール経営には、経営哲学そのものに根本的な違いがあります。
この違いを理解することで、なぜ現代の企業がアジャイル型への転換を求められているのかが明確になります。
実は、多くの日本企業が気づかないうちにウォーターフォール経営の限界に直面しているのです。
計画重視型と実行重視型の根本的差異
ウォーターフォール経営では、詳細な中長期計画の策定が経営の出発点となります。
一般的には年度初めに綿密な事業計画を立て、その計画に従って1年間実行するのが基本的な流れです。
一方、アジャイル経営では「実行しながら計画を修正する」というアプローチを取ります。
例えば、新規事業開発において従来型では市場調査から事業計画書作成まで6カ月かけて準備します。
しかしアジャイル経営では、1カ月で最小限の試作品を作り、実際に顧客に使ってもらいながら事業の方向性を決定していきます。
この違いは「完璧な計画を求める文化」と「素早い学習を重視する文化」の差とも言えるでしょう。
意思決定プロセスとスピードの違い
ウォーターフォール経営では、重要な意思決定は経営層が行い、現場はその指示に従って実行する仕組みです。
意思決定には複数の承認プロセスが必要で、稟議書の作成から最終承認まで数週間から数カ月を要することも珍しくありません。
アジャイル経営では、現場のスクラムチームが迅速に意思決定を行う権限を持ちます。
具体的には、チーム内で議論して決定した内容については、上司の承認を得ることなく即座に実行に移せます。
例えば、顧客からのクレーム対応において、従来なら上司への報告・相談・承認を経て対応策を実行しますが、アジャイル型では現場チームが即座に改善策を実施できます。
この結果、意思決定のスピードが従来の10倍以上向上することも報告されています。
組織構造と権限分散の考え方
ウォーターフォール経営の組織は、明確な階層構造とピラミッド型の指揮命令系統が特徴です。
各部門は縦割りで運営され、部門間の連携は主に管理職を通じて行われます。
アジャイル経営では、部門の壁を越えたフラットなネットワーク型組織を構築します。
意外にも、この組織形態は戦国時代の日本軍が採用していた「一所懸命」の考え方と類似しています。
各スクラムチームは、あたかも独立した小さな会社のように機能し、それぞれが明確な目標に向かって自律的に行動します。
権限も従来の「上司が決める」から「チーム全員で決める」へと根本的に変化し、一人ひとりの責任感と当事者意識が格段に向上するのです。
アジャイル経営が注目される理由
アジャイル経営への関心が急速に高まっている背景には、現代のビジネス環境が抱える3つの重要な変化があります。
これらの変化は、従来の経営手法では対応が困難な新たな課題を企業に突きつけています。
実は、多くの経営者が感じている「経営の難しさ」の根本原因は、この環境変化にあるのです。
VUCA時代の不確実性への対応力
現代は「VUCA時代」と呼ばれる、変動性・不確実性・複雑性・曖昧性に満ちた時代です。
一般的には経営環境の変化は予測可能と思われがちですが、実際には新型コロナウイルスのような予期せぬ出来事が頻繁に発生します。
アジャイル経営は、このような予測困難な状況への対応力を格段に向上させます。
例えば、2020年のパンデミック発生時、従来型経営の企業は既存の年間計画に固執し、対応が後手に回りました。
一方、アジャイル経営を実践していた企業は、わずか数週間でリモートワーク体制を整備し、新たなビジネスモデルを構築しました。
この差は「計画の変更を嫌う文化」と「変化を機会と捉える文化」の違いから生まれています。
顧客ニーズの急速な変化に対応
現代の顧客ニーズは、従来の年単位ではなく月単位、時には週単位で変化しています。
特にデジタルサービスでは、顧客のスイッチングコストが極めて低く、満足できないサービスからは即座に離脱します。
アジャイル経営では、この「顧客価値競争」に対応するため、継続的な顧客との対話を重視します。
具体的には、サービスリリース後も定期的に顧客の声を収集し、2週間~1カ月という短期間で改善を実施します。
例えば、あるSaaS企業では、顧客からのフィードバックを受けて機能改善を行う頻度が、従来の年4回から月2回に増加しました。
意外にも、この頻繁な改善により顧客満足度が大幅に向上し、解約率が半分以下に減少したのです。
DX推進における重要性の高まり
デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進において、アジャイル経営は不可欠な要素となっています。
経済産業省の「DXレポート2.0」でも、DX成功の鍵としてアジャイルなアプローチの重要性が明記されています。
従来のシステム開発では、要件定義から運用開始まで2~3年を要することが一般的でした。
しかしアジャイル経営では、最小限の機能から始めて段階的に拡張するアプローチを取ります。
例えば、ある製造業では、全社システムの一括刷新を諦め、部門別に小規模なデジタル化を段階的に実施しました。
この結果、当初予定していた3年ではなく、わずか8カ月で全社のデジタル化を達成し、投資効果も当初計画の3倍を実現したのです。
アジャイル経営を実践している主要企業
アジャイル経営の実践は、もはやスタートアップ企業だけの取り組みではありません。
大手企業から中小企業まで、幅広い業界で導入が進んでおり、それぞれ独自のアプローチで成果を上げています。
実は、日本企業の中にもアジャイル経営で大きな変革を遂げた先進事例が数多く存在します。
ユーザベースの顧客起点アジャイル経営
株式会社ユーザベースは、アジャイル経営の日本における代表的な実践企業です。
同社はNewsPicksやSPEEDAといった情報プラットフォームを運営し、「顧客起点で変化にスピーディに対応する経営」を実践しています。
特徴的なのは、経営企画部が「アジャイル経営のコーチ」としての役割を果たしていることです。
具体的には、経営層と現場をつなぎ、各チームの意思決定をサポートすることで「計画と実行の分離」を解消しています。
例えば、新機能開発において、従来なら経営企画部が年間計画を策定し現場が実行していました。
しかしアジャイル型では、現場チームが顧客との対話から得た洞察をもとに、経営企画部と協力して迅速に戦略を修正します。
この結果、顧客のニーズ変化に対する対応スピードが従来の5倍以上向上したと報告されています。
KDDIの大企業アジャイル経営変革
KDDI株式会社は、大手通信事業者としてアジャイル経営への組織変革を成功させた代表例です。
同社では、ソフトウェア開発にとどまらず、組織運営そのものにアジャイルの考え方を導入しています。
意外にも、この変革を主導したのはGoogleから転職した藤井彰人氏で、外部の視点を活用した改革でした。
重要なポイントは、全社一律の変革ではなく、小規模なパイロットチームから段階的に拡大したことです。
例えば、最初は4名程度の小さなスクラムチームを編成し、新サービス開発で成果を実証しました。
その成功事例をもとに、徐々に他部門にもアジャイルな働き方を展開し、現在では数百名規模での運用を実現しています。
海外企業の先進的アジャイル経営
海外では、アジャイル経営がより広範囲で実践されており、日本企業にとって参考となる事例が数多くあります。
アメリカの3M社では、スクラム導入により業務効率が300%向上したという驚異的な成果が報告されています。
この成果の背景には、従業員の働き方そのものを根本的に見直したことがあります。
具体的には、従来の年次評価制度を廃止し、短期間での目標設定と振り返りを繰り返すシステムに変更しました。
また、BMWのような自動車メーカーでさえ、財務計画にアジャイルの考え方を取り入れ始めています。
従来のウォーターフォール型予算管理では、年度末に不要な支出が発生し数十億ドルの無駄が生じていましたが、アジャイル型では四半期ごとの柔軟な予算見直しにより、この問題を大幅に改善しました。
アジャイル経営の具体的な活用事例
アジャイル経営の理論を理解しても、実際の業務にどう活用するかが最も重要なポイントです。
ここでは、具体的なビジネスシーンでの活用方法を、実際の企業事例をもとに詳しく解説します。
実は、アジャイル経営は特別な業種や規模の企業だけでなく、あらゆる組織で応用可能な汎用性の高い手法なのです。
新サービス開発でのアジャイル経営活用
新サービス開発において、アジャイル経営は従来のプロセスを根本的に変革します。
従来なら市場調査から設計、開発、テストまでを順次実行し、完成品をリリースするのが一般的でした。
アジャイル経営では、最小限の機能を持つ「MVP(最小実行可能製品)」を短期間で開発し、実際の顧客に使用してもらいます。
例えば、あるFintech企業では、新しい家計簿アプリの開発に従来なら1年を要していました。
しかしアジャイル型では、基本的な収支記録機能のみを2カ月で開発し、100名のモニターユーザーに提供しました。
その結果、当初想定していなかった「写真でレシート読み取り機能」のニーズが判明し、追加開発によって競合他社との差別化に成功したのです。
組織改革におけるアジャイル経営実践
組織改革の分野でも、アジャイル経営の考え方が大きな効果を発揮しています。
従来の組織改革は、コンサルティング会社が作成した詳細な改革計画を段階的に実行するアプローチが主流でした。
アジャイル経営では、小さな改善を継続的に実施し、その効果を検証しながら組織を進化させます。
具体的には、部門間のコミュニケーション改善を目的として、まず週1回の合同ミーティングから始めます。
その効果を2週間で検証し、好評であれば頻度を増やし、課題があれば形式を変更するという柔軟なアプローチを取ります。
意外にも、このような小さな変化の積み重ねが、6カ月後には組織全体の生産性を30%向上させた事例も報告されています。
危機対応でのアジャイル経営機動力
危機対応において、アジャイル経営の真価が最も発揮されます。
2020年のコロナ禍では、アジャイル型組織と従来型組織の対応力に歴然とした差が現れました。
アジャイル経営を実践していた企業は、わずか1~2週間でリモートワーク体制を整備し、新たなビジネスモデルを構築しました。
例えば、ある飲食チェーンでは、店舗営業停止という危機に直面した際、各店舗が独立した小さなスクラムとして機能しました。
本部からの指示を待つのではなく、各店舗が地域の状況に応じてテイクアウト専門店への転換、デリバリーサービスの開始、食材販売など多様な施策を即座に実行しました。
この結果、業界全体が売上減少に苦しむ中、同チェーンは前年同期比110%の売上を維持することに成功したのです。
まとめ【アジャイル経営で変化に強い組織を】
アジャイル経営は、変化の激しい現代において企業が持続的な成長を実現するための重要な経営手法です。
ソフトウェア開発から生まれたこの手法は、小規模なスクラムチームによる自律的な意思決定と、短期間での実行・検証サイクルを特徴としています。
従来のウォーターフォール経営との最大の違いは、「計画よりも変化への対応」を優先し、顧客との継続的な対話を通じて価値を創造することです。
VUCA時代の不確実性、顧客ニーズの急速な変化、DX推進の必要性という3つの環境変化により、アジャイル経営への注目が高まっています。
ユーザベースやKDDIなどの先進企業では、既に大きな成果を上げており、海外企業でも業務効率の大幅改善が報告されています。
新サービス開発、組織改革、危機対応など様々な場面で活用でき、継続的な改善により組織全体の対応力が向上します。
アジャイル経営は、企業規模や業種を問わず適用可能な汎用性の高い経営手法として、今後ますます重要性が高まっていくと考えられます。