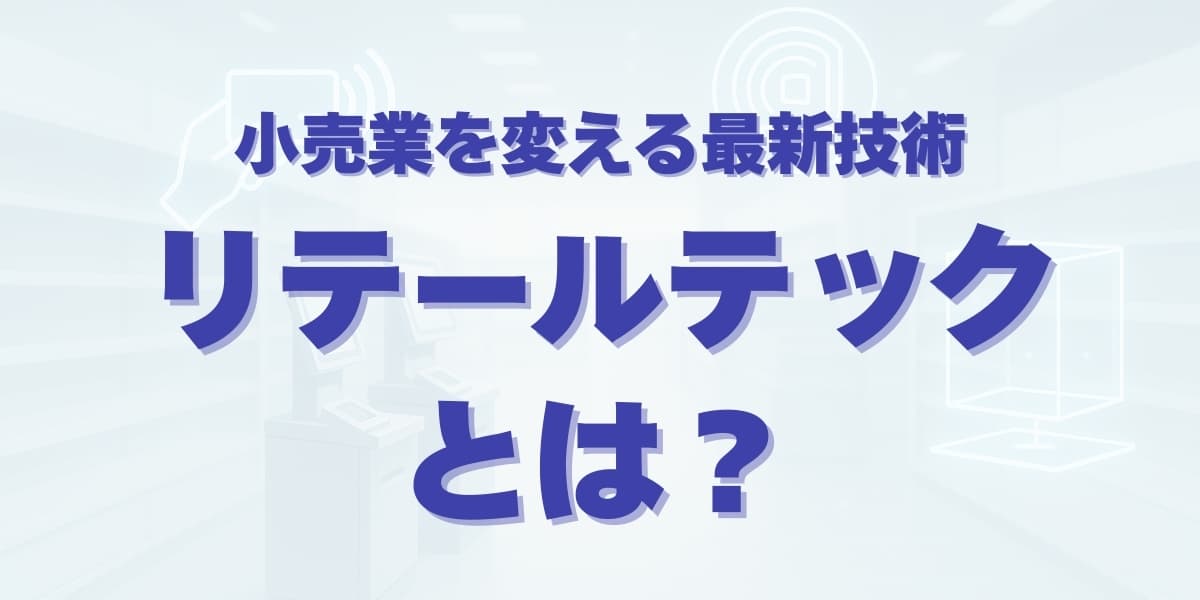「リテールテックって最近よく聞くけど、何のこと?」「セルフレジとかキャッシュレス決済も関係あるの?」「小売業にどんな変化をもたらすの?」
このような疑問を持つ方は多いのではないでしょうか?
リテールテックとは、小売業にIT技術を導入して業務効率化や顧客体験向上を図る取り組みです。セルフレジやキャッシュレス決済、無人店舗など、すでに私たちの身近な場所で活用されています。
本記事では、リテールテックの基本的な仕組みから最新の活用事例まで分かりやすく解説します。理解することで、今後の買い物体験の変化を予測でき、小売業界の技術革新の全体像も掴めるでしょう。
この記事で分かること
・リテールテックの基本概念と仕組み
・従来の小売業との具体的な違い
・主要企業の導入事例と最新技術動向
分かりやすく解説しているので、ぜひお読みください。
目次
リテールテックとは?小売業界で注目される技術解説
リテールテックは、小売業を意味する「リテール(Retail)」と技術を意味する「テクノロジー(Technology)」を組み合わせた造語です。小売業にIT技術を導入し、業務効率化や顧客体験向上を実現する取り組み全般を指します。
現在では、コンビニのセルフレジやスマホ決済など、私たちの日常生活にも深く浸透している技術です。
リテールテックの基本的な仕組みと特徴
リテールテックの基本的な仕組みは、AI・IoT・ビッグデータなどの最新技術を小売業務に組み込むことです。小売業にIT(情報技術)を導入すること。また、それによって実現する新たなサービスやビジネス。流通・決済・在庫管理・物流管理などに各種IoT機器を利用したり、人工知能を活用したりすることをさす。
従来の人手に依存していた作業を自動化し、データに基づいた正確な判断を可能にします。店舗運営から顧客サービスまで、小売業の幅広い領域で活用されています。
最大の特徴は、店舗スタッフと顧客の両方にメリットをもたらすことです。スタッフの業務負担を軽減しながら、顧客により便利で快適な買い物体験を提供できます。
従来の小売業務とリテールテックの違い
従来の小売業務は、レジ作業や在庫管理など多くの作業を人手で行っていました。これに対しリテールテックでは、セルフレジやRFID技術による自動化が進んでいます。
人による作業をIT技術が代替することで、スタッフの業務負荷やヒューマンエラーを低減できるほか、待ち時間の解消などによる顧客満足度の向上も見込める。在庫管理も、従来の目視確認からセンサーによるリアルタイム監視に変化しています。
データ活用の面でも大きな違いがあります。従来は売上データの集計に時間がかかっていましたが、現在はPOSシステムによる即座のデータ収集・分析が可能です。
リテールテックが実現する新しい買い物体験
リテールテックにより、顧客はより個別最適化された買い物体験を享受できるようになりました。AI分析による商品推奨や、スマホアプリと連携した店内ナビゲーションが代表例です。
決済方法も大幅に進化し、キャッシュレス決済や無人レジにより、レジ待ち時間の大幅短縮を実現しています。キャッシュレス決済により、お金を持ち歩く必要がなくなり、消費履歴もすぐに確認できる。
オンライン接客サービスでは、自宅にいながら専門スタッフによる商品説明を受けられます。リアル店舗とオンライン販売の境界線が曖昧になり、時間や場所に縛られない新しい購買スタイルが生まれています。
これまでの小売業とリテールテックとの違い
従来の小売業とリテールテックを導入した現代の小売業では、業務プロセスや顧客体験に大きな変化が生まれています。特に作業の自動化、データ活用、個別対応の3つの領域で顕著な違いが見られます。
これらの変化により、小売業界全体の効率性と顧客満足度が大幅に向上しています。
従来の人的作業から自動化システムへの転換
従来の小売業では、商品の入荷から販売まで多くの作業を人手に依存していました。レジ業務、在庫確認、商品陳列など、スタッフが直接対応する必要がありました。
リテールテックの導入により、これらの作業は大幅に自動化されています。セルフレジの普及により、顧客自身が商品スキャンと決済を行えるようになりました。
RFID技術を活用した在庫管理では、商品タグを一括スキャンすることで瞬時に在庫状況を把握できます。従来の目視による棚卸作業と比較して、作業時間は約3分の1に短縮されています。
データ活用による経営判断の精度向上
従来の小売業では、売上データの集計や分析に時間がかかり、リアルタイムでの経営判断が困難でした。手書きの売上記録や、週単位・月単位での集計が一般的でした。
現在のリテールテックでは、POSシステムとクラウド技術により即座のデータ収集・分析が可能です。販売データを自動で収集・蓄積することができます。従来のアナログの手書き記録と比べて、正確なデータを効率的に集められる。
商品別売上、時間帯別来店数、顧客の購買パターンなど詳細な分析により、在庫調整や販促活動の精度が大幅に向上しています。データに基づいた科学的な店舗経営が実現できています。
顧客体験の個別最適化技術の進歩
従来の小売業では、すべての顧客に対して画一的なサービスを提供していました。商品推奨や接客対応も、スタッフの経験や勘に頼る部分が大きかったのが現実です。
リテールテックにより、顧客一人ひとりの購買履歴や嗜好を分析した個別対応が可能になりました。AIが過去の購入データを分析し、最適な商品を推奨する仕組みが構築されています。
スマホアプリと連携したパーソナライズサービスでは、来店前から個人の好みに合わせた特別オファーを受け取れます。オンライン接客サービスにより、専門知識を持つスタッフとリモートで相談できる環境も整っています。
リテールテックが注目される理由
リテールテックが急速に注目を集める背景には、小売業界を取り巻く環境の大きな変化があります。人手不足の深刻化、消費者行動のデジタル化、そして感染症対策への需要が主な要因です。
これらの課題に対する解決策として、リテールテックの導入が不可欠になっています。
深刻化する人手不足への対応策
日本では少子高齢化により労働人口が減少の一途を辿っており、どの業界でも人手不足の課題を抱えています。特に小売業では、店舗人材の不足により営業時間の短縮を余儀なくされるなど、売上減少の深刻化が予測されています。
リテールテックの導入により、限られた人員でも効率的な店舗運営が可能になります。セルフレジの活用など、少ない人材でも今まで通りに小売業ができることから、リテールテックは一気に注目を集めました。
業務の自動化により、スタッフはより付加価値の高い接客業務に集中できるようになります。人手不足解消に寄与し、さらに増加する訪日外国人客に利便性を提供する手段としてキャッシュレス化は注目を集めています。
消費者行動の変化とデジタル化の進展
スマートフォンの普及により、消費者の購買行動は大きく変化しています。商品の事前調査、価格比較、口コミ確認など、購入前のデジタル行動が当たり前になりました。
ECサイトでの買い物体験に慣れた消費者は、実店舗でも同等の利便性を求めるようになっています。商品情報の詳細表示、スムーズな決済、個別対応サービスなどへの期待が高まっています。
リテールテックにより、オンラインとオフラインの境界線を超えた統合的な顧客体験が実現できます。スマホアプリと連携した店内ナビや、デジタルサイネージによる商品情報提供など、デジタルネイティブ世代のニーズに応える仕組みが構築されています。
コロナ禍による非接触ニーズの高まり
2020年に起こった世界的なコロナウイルスの蔓延により、社会全体の仕組みが大きく変わり、私たちはできる限り人同士の非接触が求められるようになりました。そこで注目されたのがリテールテックです。
従来の対面接客から、非接触での商品購入やサービス利用への需要が急激に拡大しました。キャッシュレス決済、セルフレジ、オンライン接客など、人との接触を最小限に抑える技術が重視されています。
リテールテックは人と人が接触する機会を最大限減らせることから、現代社会の情勢に相応う小売として注目を集めるようになりました。感染症対策と利便性向上を同時に実現できる点で、継続的な導入価値が認められています。
リテールテックを開発・提供している主要企業
リテールテック分野では、世界的なIT企業から国内の老舗メーカーまで幅広い企業が技術開発に取り組んでいます。海外では先進的な無人店舗技術、国内では実用性重視のシステム開発が特徴的です。
新興企業による革新的なソリューションも注目を集めており、競争が激化しています。
Amazon・ウォルマートなど海外先進企業
アメリカのAmazonはリテールテック分野の先駆者として知られており、2018年にシアトルでオープンしたAmazon Goが代表的な事例です。店内に搭載されたセンサーカメラなどとスマートフォンアプリを連携することで、従来のレジにおけるスキャンや決済の手間を省いている。
世界最大のスーパーマーケットチェーンであるウォルマートも、VR技術を従業員研修に活用するなど積極的な取り組みを進めています。日々のトレーニングや管理職の昇進試験などにVRを導入しています。
中国のアリババグループは、顔認証技術と決済システムを組み合わせた無人コンビニを展開中です。これらの企業は、技術革新により小売業界の未来像を切り開いています。
東芝テック・NEC・イオンなど国内大手企業
国内では東芝テックがPOSシステムやセルフレジ分野で長年の実績を持ち、リテールテック関連機器の開発・製造を手がけています。RFID技術を活用した在庫管理システムなど、実用性の高いソリューションを提供しています。
NECは顔認証技術やAI分析システムを活用した店舗運営支援サービスを展開中です。顧客の行動分析や混雑状況の把握により、店舗効率化を支援しています。
イオングループでは、自社のイオンスマートテクノロジーを通じて5000店舗とデジタルを結ぶ取り組みを推進しています。お客さま視点で5000店舗とデジタルを結ぶ小売ビジネスを支えるイオンスマートテクノロジーのリアルと挑戦を進めています。
スタートアップ企業の革新的技術開発
リテールテック分野では、多くのスタートアップ企業が革新的な技術開発を進めています。シリコンバレー発の体験型ストアb8taは、「RaaS(Retail as a Service)」と呼ばれる新しいビジネスモデルを提案しています。
日本国内でも、AI技術やIoT技術を活用した店舗分析サービスを提供する企業が相次いで設立されています。店舗内の顧客動線分析や、商品配置の最適化提案など、データドリブンなソリューションが特徴です。
これらのスタートアップ企業は、大手企業では実現が困難な柔軟性を活かし、ニッチな課題解決や新しい顧客体験の創出に取り組んでいます。技術革新のスピードも速く、小売業界の変革を牽引する存在として注目されています。
リテールテックの活用事例
リテールテックは既に私たちの日常生活に深く浸透しており、スーパーやコンビニ、アパレル店など様々な業界で実用化されています。身近な決済システムから最先端の無人店舗まで、多岐にわたる活用事例があります。
これらの技術により、店舗運営の効率化と顧客満足度向上の両方が実現されています。
セルフレジ・キャッシュレス決済の普及
スーパーマーケットやコンビニエンスストアを始め、大手量販店などで導入が進んでいるセルフレジは、リテールテックのひとつです。顧客が自分で商品のバーコードを読み取りして料金を支払う形態だけでなく、アパレルなどではRFIDタグを用いてバーコードを読み取らずに支払い料金を確定させるセルフレジも登場しています。
キャッシュレス決済も急速に普及が進んでおり、2018年6月時点で約24%だった利用率は年々上昇しています。クレジットカード決済、電子マネー決済、スマートフォンを使ったコード決済など、現金を出さずにワンタッチで会計を済ませることで、レジ待ち行列を解消している。
これらの技術により、スタッフの作業負担を軽減し、人手不足を解消することに役立っています。顧客側も待ち時間の短縮というメリットを享受できています。
RFID・AIによる在庫管理システム
RFID(Radio Frequency Identification)とは、電波による無線データの読み取りを介し、商品を識別・管理するシステムです。大手衣料品店ではRFIDを導入し、専用スペースに入れた商品情報タグを読み取る仕様にしたことで、会計業務の大幅な効率化に成功しています。
AI技術を活用した需要予測システムでは、過去の売上データや天候情報、イベント情報などを総合的に分析します。これにより、商品の発注量や陳列計画の精度が大幅に向上しています。
物流倉庫では、**RPA(Robotic Process Automation)**の導入により商品管理から入荷作業、ピッキング、検品など、一連の作業をロボット化できれば、現場で働く作業スタッフにかかる過剰な業務負荷は大きく改善されます。
無人店舗・オンライン接客サービス
Amazon Goに代表される無人店舗はリテールテックの最先端事例として注目されています。店内のカメラやセンサーが顧客の行動を追跡し、手に取った商品を自動で認識して決済を行います。
国内では伊勢丹新宿店でランドセルのオンライン接客を開始するなど、リモート接客サービスが拡大しています。販売員はタブレット端末越しに顧客と対面し、質問に答えながら商品の紹介をしていくという。
IoTデバイスによる店舗の省エネ管理や、AIチャットボットによる24時間顧客サポートなど、新しいストア形態や消費者体験の創出が進められています。これらの技術により、時間や場所の制約を超えた新しい買い物体験が実現されています。
まとめ【リテールテックで変わる小売業の未来】
リテールテックは、小売業にIT技術を導入して業務効率化と顧客体験向上を実現する取り組みです。セルフレジやキャッシュレス決済といった身近な技術から、AI在庫管理や無人店舗まで、幅広い分野で活用されています。
人手不足の深刻化、消費者行動のデジタル化、非接触ニーズの高まりを背景に、小売業界における技術導入は加速しています。Amazon・ウォルマートなどの海外企業から、東芝テック・NECなどの国内企業まで、多様な企業が革新的な技術開発を進めています。
今後もAI技術の進歩やIoTデバイスの普及により、リテールテックはさらなる発展を遂げると予想されます。小売業界の変革を理解することで、私たち消費者も新しい買い物体験の変化に適応していくことができるでしょう。